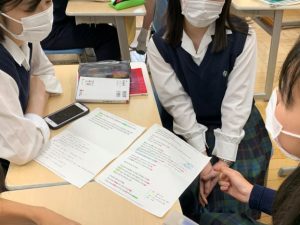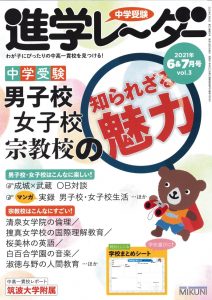ありのままの自分とは? 中2担任 杉山知子
【聖書】ヨハネによる福音書20章17節~23節
イエスは言われた。「わたしにすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ上っていないのだから。わたしの兄弟たちのところへ行って、こう言いなさい。『わたしの父であり、あなたがたの父である方、また、わたしの神であり、あなたがたの神である方のところへわたしは上る』と。」
マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、「わたしは主を見ました」と告げ、また、主から言われたことを伝えた。
その日、週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへ、イエスが来て真ん中に立ち、「あなたがたに平和があるように」と言われた。そう言って、手とわき腹とをお見せになった。弟子たちは、主を見て喜んだ。
イエスは重ねて言われた。「あなたがたに平和があるように。父がわたしをお遣わしになったように、わたしもあなたがたを遣わす。」
そう言ってから、彼らに息を吹きかけて言われた。「聖霊を受けなさい。だれの罪でも、あなたがたが赦せば、その罪は赦される。だれの罪でも、あなたがたが赦さなければ、赦されないまま残る。」
********************************************
昨日から保護者の方々と懇談する保護者面談が始まりました。
毎年とても楽しみにしています。
私のトシだと、正直、中学生の皆さんより保護者の皆さまの方が年齢が近くて話も合うことが多いですからね。
保護者の方々に対して何よりもまず感じるのは感謝です。
赤ちゃんだった皆さんを死なせないように世話してくださって、小学生になったら宿題を手伝ったりしてくださって、捜真を受験させてくださったからこそ、こうして中学生になった皆さんに会うことができたのですから。
今週の初めまでうちに娘と孫が来ていたので、赤ちゃんを死なせないように世話するのがいかに大変か、改めて実感しました。
娘は出産後3日間は輸血やら点滴やらにつながれていておっぱいをあげることができず、退院後も再入院したりと不調が続きました。それで、うちに来たばかりのときはおっぱいの出が悪くて、赤ちゃんはうまく飲めずにギャーギャー泣いてばかりいました。幸い良い母乳相談室に行くことができて飲めるようになってきましたが、今度は鼻くそがつまって苦しくて飲めないから耳鼻科で軟膏をもらわなくちゃとか、うんちが出なくて不機嫌だから浣腸しなくちゃとか、まあ、次々とトラブルが起こるのです。ありがたいことに赤ちゃんは我慢せずにいちいちギャーギャー泣いてくれるので、1つ1つなんとか解決することができ、体重も順調に増えて1ヵ月検診を迎えることができました。なにしろ赤ちゃんはおっぱいやミルクを飲めなければ死にますからね。皆さんが赤ちゃんのときも、小さなトラブルから大きな病気までいろいろあったに違いありません。皆さんはギャーギャー泣くしかなかったと思いますが、お母さんやお父さんが睡眠時間を削って1つ1つ解決してくださったからこそ、皆さんは今、生きているのです。
ところで、先日ある人と話をしていたら、話の流れの中でその人が「ありのままの自分って···何なんでしょうね···」みたいなことをつぶやきました。
「ありのままの自分」、「ありのままのあなた」というフレーズはよく聞きますよね。「ありのままの自分を受け入れよう」とか、「神さまはありのままのあなたを愛している」とか。
でも、何となく、「ありのままの自分」という固定した「自分」があるようなニュアンスで使われてはいないでしょうか。
そうすると、「今の私はありのままの自分ではないのではないか」、「もっとありのままの自分でいなくてはならないのではないか」などと心配になったりするわけです。
でも、実は、固定した「自分」なんてものはありません。
そもそも細胞が刻一刻と入れ替わっているのですから、生物としても同じ自分なんてありえません。
赤ちゃんは成長が早いので、毎日30グラムくらいずつ体重が増えて、1ヵ月で約 1. 3 倍、3ヶ月で2倍にもなります。
さすがに皆さんはそこまで増えないかもしれませんが、中1中2くらいだとしばらく見ないうちにすごく背が伸びていることがありますよね。
体はもちろん、気持ちも日々変わります。
きのうはこんなこと気にならなかったのに、今日は何だかイライラするとか、逆に、以前だったら辛くなっていたかもしれないけど、最近はスルーできるようになったとか。
そう考えると、今この瞬間の自分だって「ありのままの自分」ですよね。
イライラしている自分も、スルーできている自分も、あるいは人の目を気にしてキャラを作っている瞬間の自分でさえ、それが事実なのですから文字通り「ありのままの自分」と言えます。やる気満々の自分も調子に乗っている自分も、このままではマズイと落ち込んでいる自分も、今はやる気が出ないからしょうがないと開き直っている自分も、その他どの瞬間の自分も。
赤ちゃんは、ギャーギャー泣いてもふぎゃふぎゃ甘えても、ひたむきにおっぱいを飲んでもゲップをしても、何をしてもありのままで受け入れてもらえます。生きているだけでいいのです。
成長した皆さんも、私のような大人も、神さまから見たら同じではないでしょうか。
私たちは基本まじめなので、あれもしたい、これもしなくちゃと、意欲的に生きています。がんばり過ぎて疲れてしまったり、うまくいかないとき自分を責めたり周りを恨んだりしてしまいます。でも、神さまは、「これができたら愛してあげるよ」、「がんばったら認めてあげるよ」なんておっしゃいません。赤ちゃんがひたむきにおっぱいを飲んでゲップして、ぐったりして寝ていたら、無理やり起こすことはしませんよね。神さまだって、 がんばっている私たちをいとおしげに見守り、「疲れたら休ませてあげよう」とおっしゃるのです。
神さまがそのような存在だということは、イエスさまと弟子たちを見るとわかります。
弟子たちは熱心で、ひたむきにイエスさまに従っていたはずでしたが、イエスさまが逮捕されて十字架につけられたときにはみんな逃げてしまいました。一番弟子のペトロなどは、どんなことがあってもついて行きますと意気込んでいたのに、イエスさまのことなんて知らないと3回も否定してしまいました。でも、イエスさまは、ひたむきなペトロも逃げるペトロも、 意気込んでいるペトロも 裏切るペトロも、ありのままのペトロを丸ごと受け入れてくださったのです。
今日の聖書個所では、まず、イエスさまは弟子たちを「兄弟たち」と呼んでいます。逃げてしまった彼らを責めることなく、「わたしの神はあなたがたの神」ときっぱり告げてくださっています。
ところが、マグダラのマリアが「わたしは主を見ました」と弟子たちにイエスさまからの伝言を届けたのに、弟子たちは鍵をかけて家に閉じこもっていました。すると、イエスさまは恐れでいっぱいの弟子たちの真ん中に立って、「平和があるように」と言われました。イエスさまの手の釘跡とわき腹の槍傷を見て、弟子たちはやっと主だとわかって喜びました。イエスさまがいらっしゃらなくなってどうしてよいかわからず、心細かったであろう弟子たちは、十字架で死なれたイエスさまが確かに復活なさったとわかってホッとしたのでしょう。
イエスさまは重ねて「平和があるように」と言われました。
そして、弟子たちに息を吹きかけて、閉じこもっていた弟子たちを外の世界に送り出しました。
イエスさまはもう弟子たちと一緒に地上で生活することはなくなるけれど、聖霊がずっと弟子たちの心の中にいるようにしてくださいました。ペトロのことも聖霊によって見守り続けてくださったので、ペトロは他の弟子たちとともに教会の土台を作ることができたのです。先月のペンテコステは、聖霊を受けた弟子たちが教会の土台を作った記念として、教会の誕生日とも言われています。
私たちも、自分の心に鍵をかけて閉じこもってしまうことがあります。赤ちゃんのようにギャーギャー泣いてしまうわけにもいかず、どうせだれも助けてくれないとあきらめてしまったりします。
そんなとき、何かがきっかけとなって心が平和になると、もう一度動き出せることがありますよね。周りの状況は何も変わっていなかったとしても、受け止め方が変わったり見え方が変わったり。
それを助けてくださるのが聖霊なのです。
今日の聖書の言葉で一番心に響いたのが23節です。「だれの罪でも、あなたがたが赦せば、その罪は赦される」···罪を赦すなんて神さましかできないはずだと思いませんか?それなのに、聖霊によって私たちが赦せばその罪は赦される、つまり神さまが赦すのと同じだというのです。ひどいことをされてすごく怒っているとき、相手を赦すなんて絶対無理と思う時がありませんか?それなのに、なぜか赦すことができる人がいます。私は最近捜真生の中で二人もそういう人を見ました。以前にも見たことがあります。聖霊の働きとしか思えません。
一方、「だれの罪でも、あなたがたが赦さなければ、赦されないまま残る」とは、これまた怖い言葉ですね。自分が赦さなくても、神さまから見れば誰でも高価で貴い存在なのだから、どうせあの人も赦されちゃうのよね、なんて思ったりしませんか?ところが、「あなたが赦さなければ罪が残る」というのです。
イエスさまは「平和があるように」と言われたけれど、平和を実際に作ることは私たち人間に託されたのです。
ただし、口先だけで言われたのではなく、私たちの真ん中に立ってくださっています。平和のない場面ではともに苦しんでくださっているのです。
よく「神さまがいるならなぜ戦争や貧困がなくならないのか」という人がいますが、殺し合いをしているのも富を独り占めしているのも人間です。
でも、互いに赦し合い分かち合うことができるのも人間なのです。
そのことを23節の言葉は教えてくれていると感じました。
最後に、マグダラのマリアに注目したいと思います。
彼女はおそらく、社会の最底辺に属する女性だったと思います。そもそも女性の地位が低く、「女と子どもを別にして5000人」などと言われる社会ですが、イエスさまの生涯を描いた映画の中で他の女性たちからも白い目で見られるシーンが出てきたりします。
そういう彼女だからこそ、ありのままの彼女を丸ごと受け入れてくださるイエスさまを全力で愛しました。
高価な香油をイエスさまに注ぎ、涙で足を洗い、髪の毛でぬぐったのもマグダラのマリアだと言われています。
人からどう思われようと、弟子たちからもったいないと文句を言われようと、イエスさまを全力で愛する彼女がありのままの彼女だったのです。
イエスさまが亡くなられたときは全力で悲しみ、復活のイエスさまに出会ったときは全力で喜びました。「わたしにすがりつくのはよしなさい」とイエスさまにたしなめられたほどです。
マグダラのマリアには恐れがありません。復活のイエスさまをまっすぐ受け入れて行動し、恐れている弟子たちに伝えました。聞いてもらえなくても行動しました。きっと、聖書に書かれていない他の場面でもたくさんの人にイエスさまの復活を伝え、力づけたのだろうと想像します。
彼女は財産も権力も何も持っていませんでした。ただ、神さまに愛されたありのままの自分でいただけでした。あとは聖霊が助けてくださいました。
私もマグダラのマリアのようでありたいと願います。