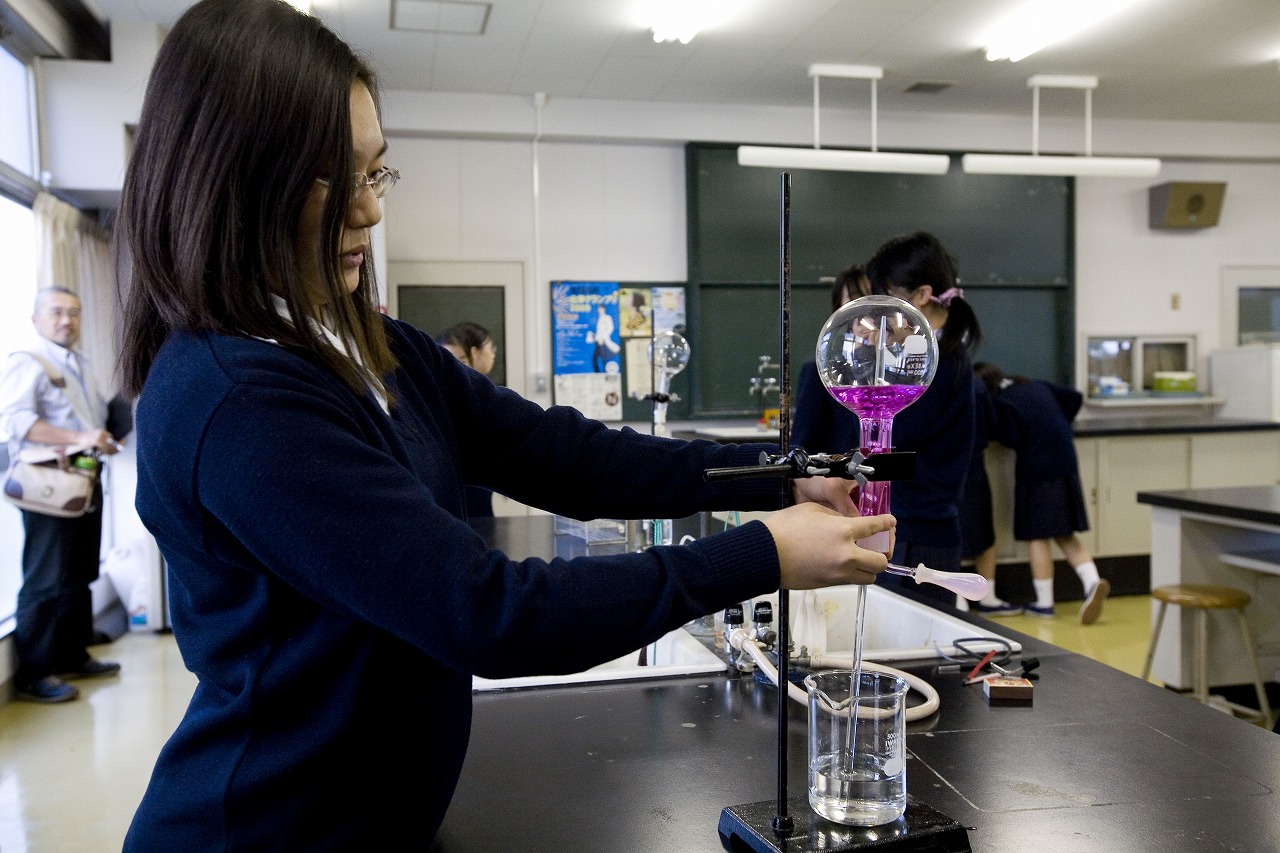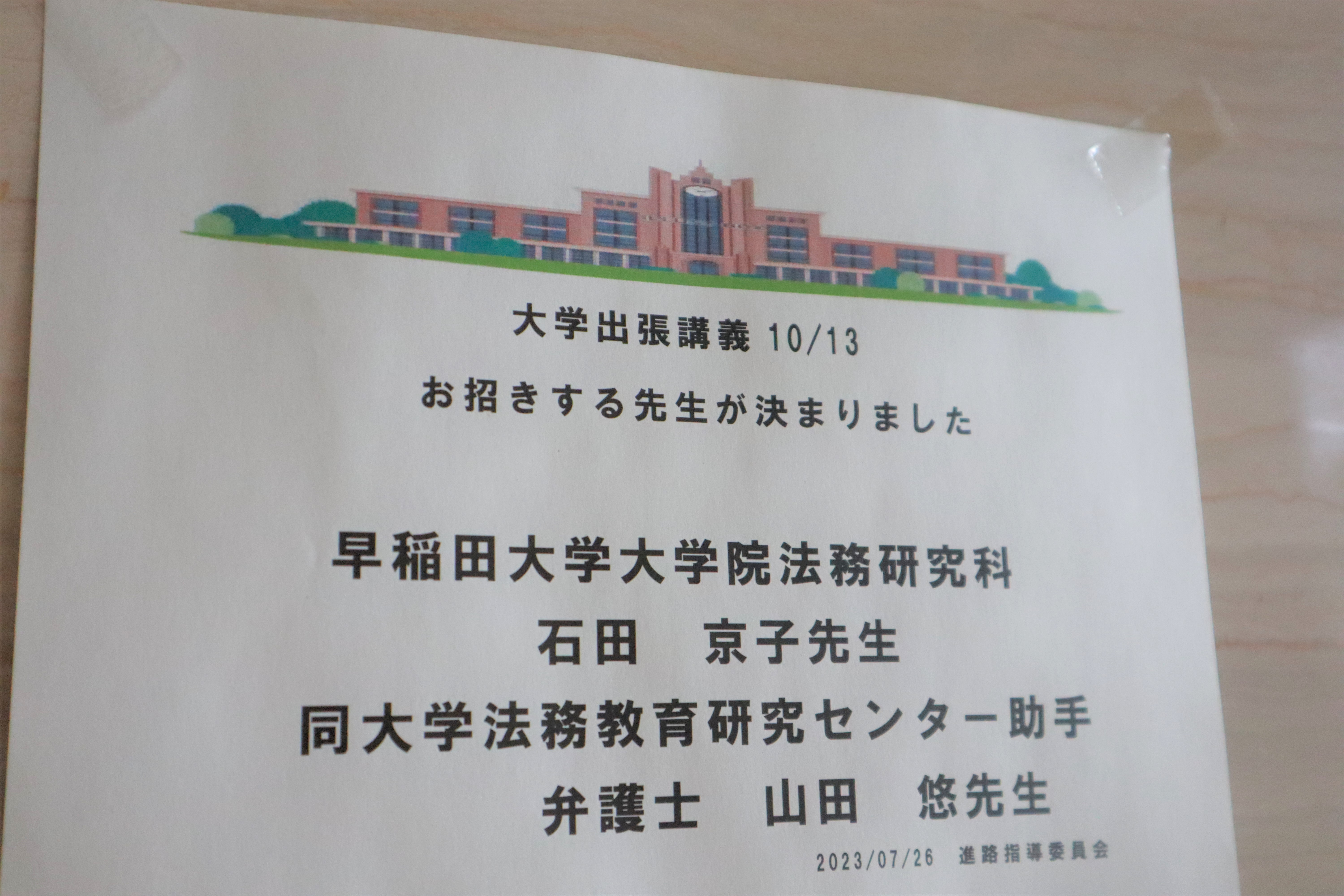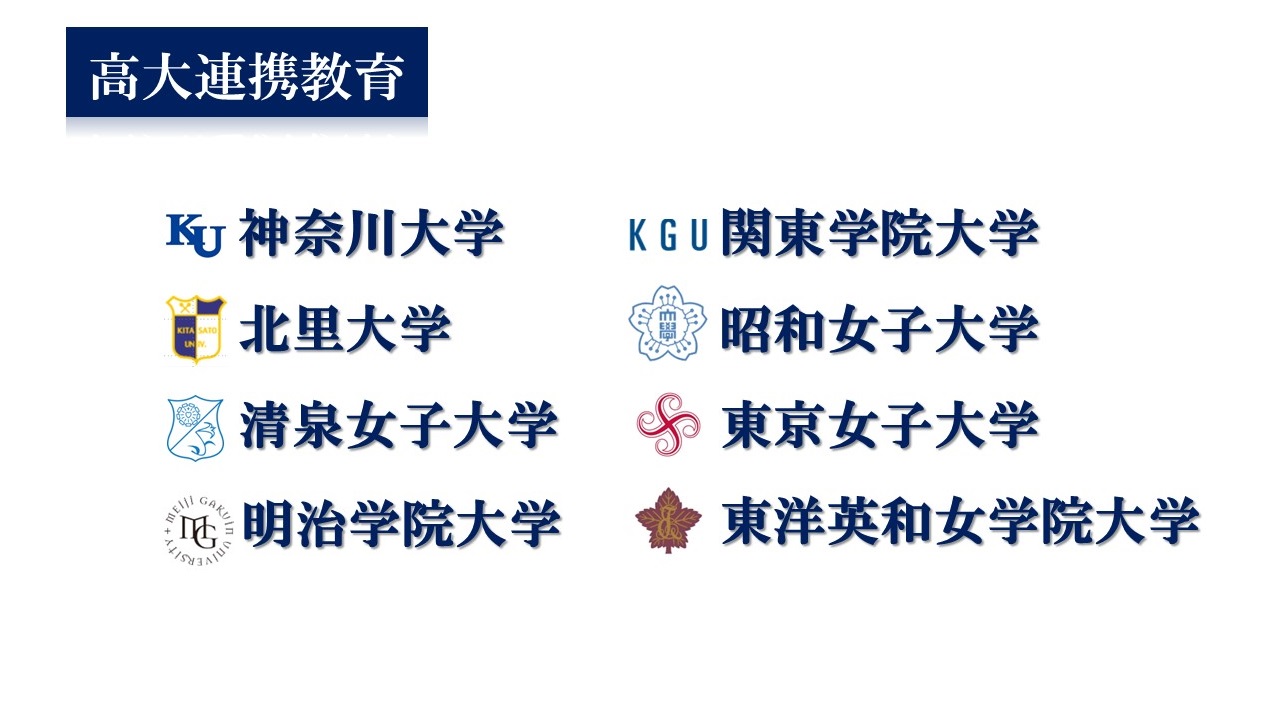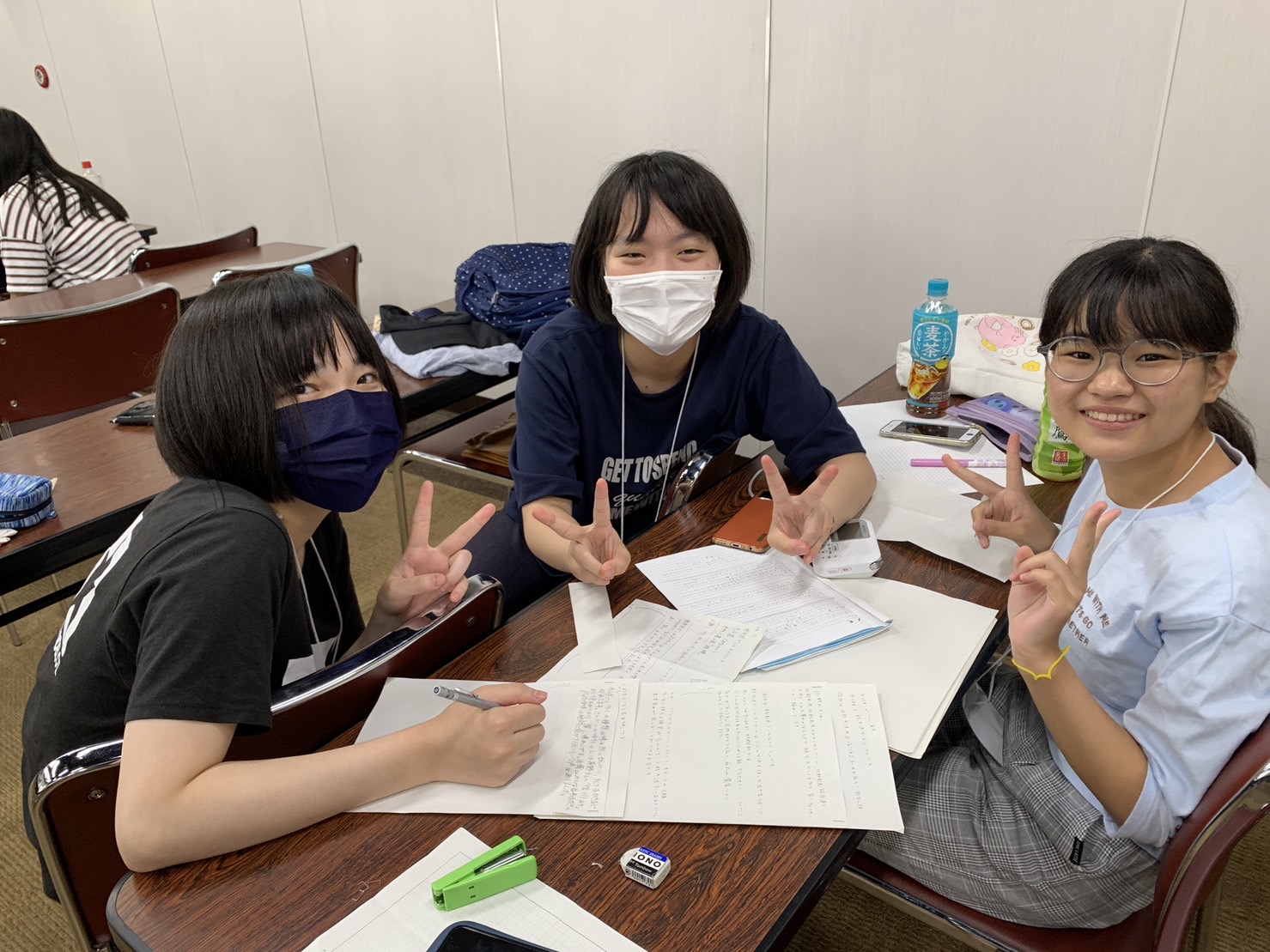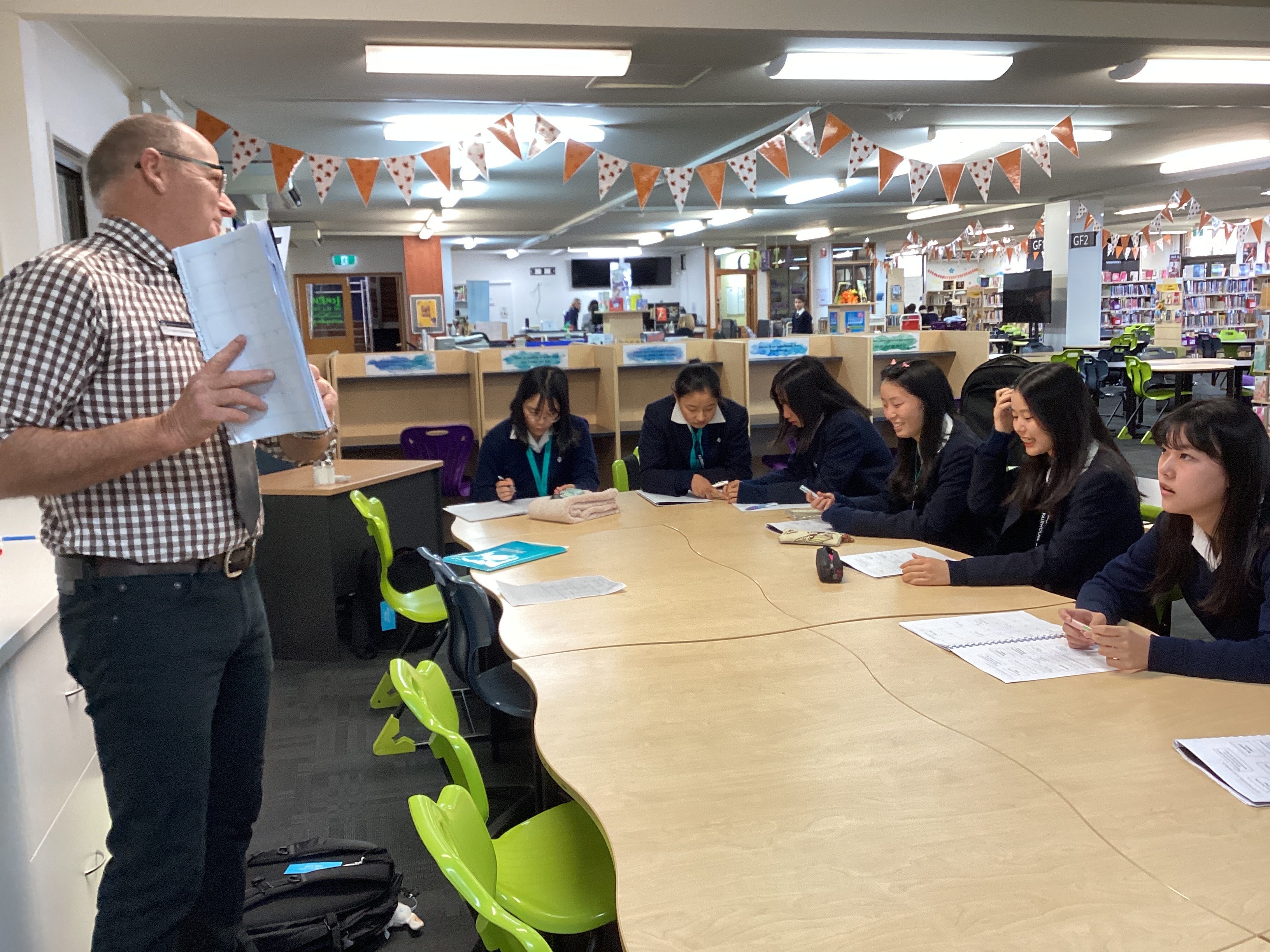9月22日(金)、23日(土·祝)の2日間、第44回捜真祭Breakthroughが行われました。
少し雨に降られた時間帯もありましたが、2日間で3388名のお客様にご来場いただきました。ご家族の方だけでなく、受験生、同窓生、生徒の友人の皆さん、捜真小学校の児童とそのご家族と、コロナ禍前のように多くの方にご来場いただきありがとうございました。
各団体長い時間をかけて準備を重ね、当日はクラブの公演や展示、各学年のお化け屋敷や縁日といったアトラクション、模擬店販売とさまざまな企画が行われました。PTAや同窓会のバザー、4年ぶりに復活した父親の会による「愛の焼き鳥」も大盛況でした。
また、1日目と2日目の間には、在校生のみの間夜祭も4年ぶりに行われ、多くの生徒が女学校体育館に集いクイズ大会などで盛り上がりました。
文化祭を陰で支えたのは、文化祭実行委員と補助役員の生徒たちです。いくつかの部門に分かれ、モニュメントやパンフレットの作成、イベントステージの運営や受付などを行い、縁の下の力持ちとして文化祭を盛り上げました。

ここ数年のコロナ禍の制限を緩和するということで試行錯誤しながら準備を進めてきましたが、結果としては、捜真生たちがさまざまな壁を突破(breakthrough)して、大きな盛り上がりを見せてくれた文化祭になりました。
改めて、第44回捜真祭Breakthroughに関わってくださったすべての方に感謝いたします。
<表彰団体>
·人気投票 公演部門
第1位 ブラスバンド部
第2位 ダンス部
第3位 弦楽部
·人気投票 展示·模擬部門
第1位 中丸病院第3·第4病棟(中3学年)
第2位 お祭り騒ぎで君を待つ(中2学年)
第3位 美術部
·イベステ賞
高三パレード
·Breakthrough賞(文化祭実行委員による投票)
The Wonderland in America 78
·ベスト81賞(中学1年生による投票)
中丸病院第3·第4病棟(中3学年)