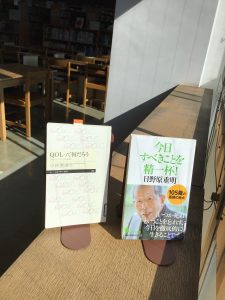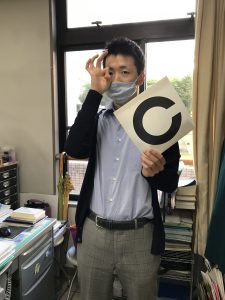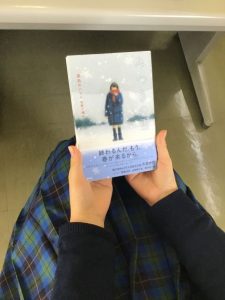KEEP EXPECTING テリオ·マイヤ
Mark 5:24b-34
“And a great crowd followed him and thronged about him. 25 And there was a woman who had had a discharge of blood for twelve years, 26 and who had suffered much under many physicians, and had spent all that she had, and was no better but rather grew worse. 27 She had heard the reports about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his garment. 28 For she said, “If I touch even his garments, I will be made well.” 29 And immediately the flow of blood dried up, and she felt in her body that she was healed of her disease. 30 And Jesus, perceiving in himself that power had gone out from him, immediately turned about in the crowd and said, “Who touched my garments?” 31 And his disciples said to him, “You see the crowd pressing around you, and yet you say, ‘Who touched me?’” 32 And he looked around to see who had done it. 33 But the woman, knowing what had happened to her, came in fear and trembling and fell down before him and told him the whole truth. 34 And he said to her, “Daughter, your faith has made you well; go in peace, and be healed of your disease.”
Do you ride a crowded train in the mornings? Have you been in Yokohama Station during rush hour? I imagine Jesus in a crowd like these. A lot of people were around him, so his disciples were surprised that he asked, “Who touched my clothes?” Of course a lot of people were touching his clothes as they walked next to him and behind him! But the scripture says that Jesus felt power go out of him when one particular woman touched his clothes. What was different about this woman? —> She had heard what other people said about Jesus. She had heard that Jesus healed people. So, she believed that he would heal her, too…even if she just touched his clothes. Although a lot of people touched Jesus’ clothes in the large crowd walking with him, they weren’t all healed or helped by Jesus that day. This woman touched Jesus’ clothes EXPECTING him to heal her, to meet her needs, to change her life. Jesus told her, “Your faith has made you well.”
About 5 years ago when I still lived in the U.S., I was a leader on a Christian retreat for high school students. One night during the retreat, all the students and leaders went outside and had time to spend with God individually. I wanted to focus my attention on God, and I didn’t want to be distracted by seeing any of the other people who were near me, so I looked straight up and stared at the sky while I talked to God. I was excited to gaze up at the stars. I was amazed, actually! I could see sooo many stars. They were bright and beautiful. I praised God for making those amazing stars. And I praised Him for the chance I had to see those stars. In my heart, I felt the Holy Spirit say— “These stars are in the sky every night. You just don’t see them, because you don’t look up.” Wow! How true! Those same bright, beautiful stars are in the sky EVERY SINGLE night, but I miss the chance to see them, because I don’t look up and EXPECT to see them.
God spoke a similar thing to me another time. When I was 23 and 24 years old, I participated in a 2-year discipleship program at my church. The first year, it was challenging, but exciting. Every week, we read books about God and faith, and we discussed them; we gathered for worship services; and we had prayer meetings. I spent a lot of time praying, reading my Bible, and worshipping God, and I experienced Him speaking to me more than ever before. After one year in the program, going to the prayer meetings, book discussions, and worship services 5-6 times per week had become a routine, and I was used to it. When my second year in the program started, at the first prayer meeting, I thought back about how I felt at the first prayer meeting of my first year; I had felt excited, expecting God to speak to me and to help me grow in my faith. But when I started my second year in the program, going to that prayer meeting felt familiar and routine. In my heart, I felt the Holy Spirit say, “Keep expecting.— Keep expecting to hear from Me. Keep expecting Me to work in your heart.”
How about you? Do you remember how you felt when you came to Soshin and attended chapel for the first time, or the whole first year? Do you remember your first class chapel service? Do you remember your first Bible classes?
—>Maybe you felt like I did when I joined the discipleship program— excited by the new experience and expecting to learn about God and to feel Him in your heart. How about now? During chapel and Bible classes, do you still expect to have new experiences with God? Do you still expect to learn something from the Bible? Do you still expect to feel Him in your heart? …Or have the Bible, prayer, and worship time become just a familiar part of your routine? As the Holy Spirit encouraged me to KEEP EXPECTING, I want to encourage you to do the same thing— KEEP EXPECTING from God. There is much more He wants to teach you and more He wants to do in your life. Hebrews 4:12 says, “the word of God is living and active…” The Bible is not just words on paper, not just stories. Those words— God’s words— are living and active. God’s Holy Spirit is also living and active. This means that even if you read or hear the same Bible story or the same Bible verses that you have read before, God can teach you something new. I have experienced this lots of times. Have you? When you go to chapel, when you are in Bible class, when you read your Bible in your free time— even if you read or hear a story or verse you have read before, KEEP EXPECTING that God will teach you and work in your heart.
—>Maybe some of you don’t think you have ever experienced God or felt the Holy Spirit speaking to your heart. Maybe— like the woman in the Bible passage— you have just heard what other people say about God. Maybe you have heard your teachers or friends, or parents or pastors tell their stories about their experiences with God, and you think— Will God speak to me, too? Will He heal me, too? Will He change my life, too? As the woman in the Bible passage did, I want to encourage you to reach out to Jesus, reach out to God with faith, EXPECTING Him to answer you.
James 4:8 says, “Draw near to God, and He will draw near to you…” Tonight or another time soon, look up at the dark night sky, and gaze at the stars. Just like the stars are in the sky every night, God is always ready to grow your relationship with Him.
<マルコによる福音書5章24節~34節>
大勢の群集も、イエスに従い、押し迫って来た。さて、ここに十二年間も出血が止まらない女がいた。多くの医者にかかって、ひどく苦しめられ、全財産を使い果たしても何の役にも立たず、ますます悪くなるだけであった。イエスのことを聞いて、群集の中に紛れ込み、後ろからイエスの服に触れた。「この方の服にでも触れればいやしていただける」と思ったからである。すると、すぐに出血が全く止まって病気がいやされたことを体で感じた。イエスは、自分の内から力が出て行ったことに気づいて、群集の中で振り返り、「わたしの服に触れたのはだれか。」と言われた。そこで、弟子たちは言った。「群集があなたに押し迫っているのがお分かりでしょう。それなのに『だれがわたしに触れたのか』とおっしゃるのですか。」しかし、イエスは触れた者を見つけようと、辺りを見回しておられた。女は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり、震えながら進み出てひれ伏し、すべてをありのまま話した。イエスは言われた。「娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさい。もうその病気にかからず、元気に暮らしなさい。」
あなたは朝の満員電車に乗っていますか?ラッシュ時に横浜駅を利用したことはありますか?私は、このような人ごみの中にいると、イエス様を想像します。聖書箇所にあるように、イエス様の周りにはたくさんの人がいたので、弟子たちはイエス様が “誰が私の服を触ったのか?”と聞いたことに驚きました。もちろん、たくさんの人がイエス様の隣や後ろを歩いていたので、当然イエス様の服を触れていたわけです。しかし、聖書によると、ある女性がイエス様の服に触れた時、イエス様は自分の内から力が出ていくのを感じたそうです。この女性は何が違ったのでしょうか?―彼女は、話すことを聞いていました。イエス様が人を癒すことができるということを。だから、彼女はイエス様が自分も癒されると信じていました…たとえ彼女がイエス様の服に触れただけでも。 イエス様と一緒に歩いている大勢の人たちの中で、多くの人がイエス様の服に触れましたが、その日、彼ら全員がイエス様に癒されたり、助けられたりしたわけではありませんでした。この女性は、イエス様が自分を癒し、必要を満たし、人生を変えてくれることを期待して、イエス様の服に触れたのです。イエス様は彼女にこう言われました。「あなたの信仰があなたを救った。」
5、6年程前、私がまだアメリカに住んでいた頃、私は高校生のためのキリスト教修養会のリーダーをしていました。修養会のある夜、全ての生徒たちとリーダーたちは外に出て、一人ひとりが神様と過ごす時間を持ちました。私は神様との時間を大切にしたいと思い、近くに他の人がいて気が散るのが嫌だったので、まっすぐ上を見上げて空を見つめながら神様に語りかけました。ワクワクしながら星を眺めていました。実際、私は驚きました。その時、たくさんの星が見えたのです。明るくてきれいでした。こんな素晴らしい星を作ってくださった神様をほめたたえました。そして、その星を見る機会を与えてくれた神様をほめたたえました。私は心の中で聖霊が語りかけるのを感じました。「これらの星は毎晩空にある。あなたが見上げていないから見えないだけだ。」と言われたのを感じました。うわー!確かにそうだ!!同じように明るくて美しい星が毎晩空にあるのに、私は見上げることも期待することもないので、見る機会を逃してしまうのです。
神様は、別の時にも同じように私に語りかけてくれました。23歳と24歳の時、私は教会の2年間の弟子訓練プログラムに参加しました。最初の年は、やりがいがあり、とても刺激的でした。毎週、神様と信仰についての本を読み、それについて話し合ったり、礼拝のために集まったり、祈りの会を開いたりしました。私はお祈りに多くの時間をかけ、聖書を読み、神様への賛美を捧げました。そして、今まで以上に神様が私に語りかけてくださることを経験しました。プログラムに参加して一年が経つと、週に5~6回の祈祷会、読書会、礼拝に行くことが日課になり、それにも慣れてきました。プログラムに参加して二年目が始まった時の最初の祈祷会で、私は一年目の最初の祈祷会に参加した時の気持ちを思い出しました。私は楽しみにしていました、神様が私に語りかけてくれることを期待し、私の信仰を強めてくださることを。しかし、二年目に入ってからは、その祈祷会に行くことが日常的に感じられるようになりました。私は心の中でふたたび聖霊が語りかけるのを感じました。「期待し続けなさい。あなたの心の中で私が働くことを期待し続けなさい。」と言っているのを感じました。
あなたはどうですか?捜真に来て初めてチャペルに参加した時、あるいは一年目の時の気持ちを覚えていますか?初めてのチャペルでの礼拝を覚えていますか?初めての聖書のクラスを覚えていますか?
きっと私が修養会に参加した時のように、あなたも新しい経験に興奮し、神様について学び、心の中で神様を感じることを期待していたのかもしれません。今はどうでしょうか?チャペルや聖書のクラスでは、今でも神様との新しい経験を期待していますか?それとも、聖書や祈り、礼拝の時間は、あなたの日課の一部になってしまったのでしょうか?聖霊が私に「期待し続けなさい。」と励ましてくださったように、私も同じように、皆さんにも「神様に期待しましょう!」と励ましたいと思います。神様はあなたに教えたいことや、あなたの人生で行いたいと思っていることがたくさんあります。
<ヘブライ人への手紙4章12節>
神の言葉は生きており、力を発揮し、どんな両刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに刺し通して、心の思いや考えを見分けることができるからです。
聖書はただの物語でもありませんし、紙の上の言葉ではありません。それらの言葉は「神の言葉」です。―言葉は生きていて、働いています。聖霊も同じように生きていて働いています。これはなにを意味するのかというと、以前に読んだり聞いたりしたことのある聖書のお話や聖句でも、神様はまた新しいことを私たちに教えてくれているということです。私はこのことを何度も経験してきました。あなたはどうですか?チャペルでの礼拝、聖書の時間、自分で聖書を開く時···聞いたことのある話や聖句だったとしても、神様があなたに教え、心の中で働いてくださることを期待し続けてください。
もしかしたら、みなさんの中には、神様の存在を経験したり、聖霊があなたの心に語りかけたりしてくるのを感じたことがないと思っている人もいるかもしれません。また、今日の聖書箇所に出てくる女性のように、他の人が神様について語っていることを聞いただけかもしれません。それとも、先生やクラスメート、両親や牧師が神との体験について語るのを聞いたことがあるかもしれません。神様は私にも語りかけてくれるのだろうか?神様は私をも癒してくれるのだろうか?私の人生も変えてくれるだろうか?聖書の一節に出てくる女性のように、私はあなたがイエス様に手を差し出し、信仰を持って神様に手を差出し、それに神様があなたに応えてくださることを期待することを励ましたいと思います。
<ヤコブの手紙4章8節>
神に近づきなさい。そうすれば、神は近づいてくださいます。
今夜、あるいは近日中に、暗い夜空を見上げて、星を見つめてみてください。星が毎晩空にあるように、神様はいつでもあなたと神様との関係を成長させてくれる準備ができているのです。