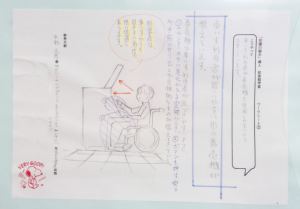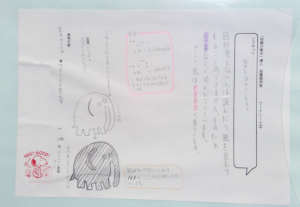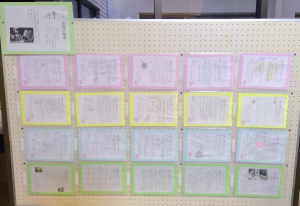投稿者「soshin」のアーカイブ
2/27(土)学校説明会の変更について
新型コロナウイルスによる現状況を考慮し、2月27日(土)に予定しておりました学校説明会は実施方法を変更し、オンラインにて本校のご案内をご視聴いただくかたちにさせていただきました。お申込いただいたご家庭にURLをメールでお伝えいたします。(当日のLive配信はございません。)
説明会当日にお配りする予定であった書類一式は郵送させていただきます。
お申込み受付期間は3月12日(金)14:00まで延長いたします。
こちらのフォームからお申し込みください。
何卒ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。
中1 オンラインホームルームでは
礼拝メッセージ 1月25日
「勉強したその先」
宗教主任 高一担任 藤本 忍
【聖書】イザヤ書35章1節~2節
荒れ野よ、荒れ地よ、喜び躍れ/砂漠よ、喜び、花を咲かせよ/野ばらの花を一面に咲かせよ。
花を咲かせ/大いに喜んで、声をあげよ。/砂漠はレバノンの栄光を与えられ/カルメルとシャロンの輝きに飾られる。/人々は主の栄光と我らの神の輝きを見る。
イザヤ書43章19節~20節
見よ、新しいことをわたしは行う。/今や、それは芽生えている。/あなたたちはそれを悟らないのか。/わたしは荒れ野に道を敷き/砂漠に大河を流れさせる。
野の獣、山犬や駝鳥もわたしをあがめる。/荒れ野に水を、砂漠に大河を流れさせ/わたしの選んだ民に水を飲ませるからだ。
********************************************
仕事柄、教会員以外の方のご葬儀の司式を引き受けることがあります。ご葬儀と言えば、通常は納棺式、前夜式、告別式、火葬式、納骨式と五回執り行われるものなのですが、昨年は火葬式だけを依頼されることがありました。火葬場に行き、讃美歌を歌い、祈りを捧げ、祝祷をしてお見送りをしました。五分程でした。ご遺族三人だけで行われ、召された方がどのようなお人柄でどのような人生を送られたのか、全くわからないご葬儀は初めてで、そして寂しいものでした。
昨年の二月末、コロナの影響で学校が休校になってから、間もなく一年が経ちます。この一年を振り返ってどう思いますか。高二は特に捜真では「華の高二」と言われていただけに、一番辛かったのではないでしょうか。「私の高二を返せ」と私の姪っ子もよく言っています。部活だけでなく、修学旅行、文化祭、体育祭と、ありとあらゆる行事が全て消えてしまって、こうなると、もう期待というものをしなくなるのではないでしょうか。また、一方では、かなり早い時期から切り替えられた人もいたのではないですか。
結果的に、やりたいと思っていたこと、やろうと思っていたことが出来なくて、そのエネルギーを今年はどこに向けましたか。勉強を始めた人も多くないですか。最初はある種の「逃げ」で始めた勉強も一山越えて意外と面白くなっている人もいると思います。やらされていた勉強が、今ではやりたくてやっていると言う人も多いと思います。コロナ禍でも将来に夢を持ち、自分の生き方にプライドを持って、納得して勉強している生徒が今年は増えた気がします。
先日たまたまTVをつけていたら、「林先生の初耳学」という番組がやっていました。ローランドとの対談でした。ローランドは「大学は空港だ」と言っていました。「行き先がわからない人は空港には行かない、行き先がわかっている、やりたいことがある人が行く」と言っていました。そして「僕は成功や結果よりやりがいを追究したい。たとえ目の前に負傷したシマウマがいても、それを襲わないライオンでいたい。勝ち方には拘りたい」とも言っていました。それに対して林先生は「そうやってやりたいことがある人はいいけど、ない人はどうすればいいの?」と聞き、続けて「僕はやりたいことに拘っていない。」と言いました。「全ては偶発的だと思っている。置かれた環境にたまたま入ってきた情報によって導かれる。今の仕事もやりたいからやったというより、『いつやるの、今でしょ』がバズって、偶然導かれてここにいる。」主体的に生きるローランドと受動的に生きる林先生、私はどちらにも共感しました。
そして、もう一人、皆に知って欲しい人がいます。それはアフガニスタンに医療活動に行って、最期はテロリストの銃弾に倒れた中村哲さんです。彼は蝶が大好きで、大変珍しい蝶がアフガンにいると聞いて現地に赴きました。しかし、干ばつが続き、子どもたちは治療しても治療しても悪化して死んでいくばかりでした。彼は言います。「医者が100人いても救えない。でも一本の水路があれば命を救える」と。そして彼はゼロから土木工学を学び六年かけて25km先の山から水路を引くことに成功しました。私が彼を尊敬してやまないのは、彼がこれまでの自分のスキルに拘らず、目の前の一人の命を救うために自分を変えることができたという点です。本当に勉強をした人というのは、自分のスキルに縋りつかず、こうやってまた一から別の分野を学び始めることができる人なのかもしれないと思いました。神様はそういう人に力を貸して下さる方です。事実、砂漠に水が流れ、花が咲いたのです。
今、皆が学んでいることが将来どのような形になっていくかなんてわかりません。しかし、自分を創造してくれた神様を信頼して最善を尽くしたいと思いませんか。なぜなら、人生の終わりなんて私たちには何もコントロールできないのですから。生きているときだけです。自分の命を何かに使える(仕える)のは。
1月25日(月)全校礼拝
みんなで取り組もうSDGs 【第10弾】
こんにちは!捜真SDGs実行委員会「みんなで取り組もうSDGs」チームです。
昨年秋から始まった、2020年度の新メンバーによる初のポスター掲示です。
通算では第10弾になります。
これからも様々な情報を提供していきたいと思います。
私たちにできるSDGsの取り組みを続けていきましょう!
【第10弾】
①プラスチックごみを減らそう!
プラスチックごみの9割がリサイクルされずに、毎年800トン以上が海に流れ込んでいます。
②知ってた?SDGs
皆さんはSDGsを知っていますか?SDGsとは「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略で2013年〜2030年の間に達成するための17の目標です。まずは知ることから始めましょう。
現時点での各国のSDGs達成率を見てみると、1位スウェーデン、2位デンマーク、3位フィンランドと北欧の国々の達成率が高くなっています。日本は17位で、目標5の「ジェンダー平等を実現しよう」目標13の「気候変動に具体的な対策を」の達成率が低くなっています。
2030年まで10年を切りました。皆で意識を高め目標達成を目指しましょう。
【第10弾のゴール目標】
図書館から本の紹介 1月16日
新しい年を迎えました。
今年も気になる本の紹介をしていきます。
冬休み中、図書館からたくさんの本を借りて家で読みました。その中で88歳の父も読んで、涙が
止まらなかったという本を紹介します。
みなさんもよくご存じの本です。
『あらしのよるに』きむらゆういち 小学館
アニメや映画、教科書にも載っている有名なお話です。絵本の第一作『あらしのよるに』は1994年、今から25年ほど前に出版されました。一時は書店にずらりと並びテレビを通してお茶の間でも話題になりました。今回は絵本ではなく、単行本をおすすめします。
今年のお正月に父が読んで、びっくりするほどのめり込み、一気に読んだと聞いてこのお話の魅力を再確認しました。
喰うか喰われるかの宿命を持つ「オオカミ」と「ヤギ」。しかしその関係を乗り越えて「友達」となり、一緒に暮らすことのできる「緑の森」を目指す。
結末は本を読んでいただきたいのですが(単行本には結末が書いてあります)、このお話がどの世代の人にも、どの時代にも必要だということをみなさんにお伝えしたいです。
命と心を震わせて生きていく人生に出会ってほしいな。
礼拝メッセージ 1月15日
「キリストの約束を信じて~分断ではなく平和を」
中1担任 杉山 知子
【聖書】ヨハネによる福音書16章33節
「これらのことを話したのは、あなたがたがわたしによって平和を得るためである。あなたがたには世で苦難がある。しかし、勇気を出しなさい。わたしは既に世に勝っている。」
********************************************
皆さん、在宅学習日を有効活用していますか?
実は、数学という教科に関しては、この学習体制はチャンスなのです。
他教科に比べて「わかる」と「できる」の差が激しく、理解するスピードなど個人差も大きいからです。
4月5月のように全部在宅だときついですが、今のように、授業で説明を聞いて「わかる」まで質問しておき、家で自分のペースでじっくり課題に取り組んで「できる」ようにするのは理想的とも言えます。いつも提出期限に追われて適当にしてしまいがちな人は、時間をかけて練習して本当の力を身につけられますね。余裕のある人は、課題以外のもっと難しい問題にも挑戦できます。数学に限らず、何か自分でテーマを決めて研究してもよいかもしれません。
日本の中高生にとって、「自分でテーマを決めて研究する」というのはあまり日常的ではないですよね。部活や委員会活動で忙しく、自由研究も小学校で終わり、というイメージです。
ところが、アメリカには「サイエンス·フェア」という科学に関する自由研究を発表する大々的な場が小·中·高にあることを、冬休みに読んだ本で知りました。高校生になって地域の大会、州の大会と勝ち進むと、世界最大のサイエンス·フェアと呼ばれる国際学生科学フェア(ISEF)に出場できます。ISEFでは1人1つのブースを与えられて、世界中から集まった専門家に自分の研究を説明するとのこと。20以上の分野で合計3億円以上と賞金額もケタ違いで、ここで賞を取った若者の中からノーベル賞受賞者が何人も出ているそうです。
でも、一部のいわゆる理系オタクたちだけのイベントというわけではなく、たとえば女優·モデルとして活躍していた高校生が思いがけないテーマと出合って勝ち進む、というエピソードもありました。そういう意味では、この本の日本語タイトル「理系の子」はちょっとずれていて、副題の「高校生科学オリンピックの青春」の方が原題の「サイエンス·フェア·シーズン」(ジュディ·ダットン著)に近いかもしれません。
ISEFには日本からも代表が派遣されていて、毎年のように受賞者がいるそうです。この本の巻末付録として2011年にアメリカ地質研究所1等賞を受賞した千葉県の女子高校生の当時の手記が載っていますが、彼女がその研究を始めたのは中1の時だそうですよ。
2012年に出版されたこの本を2021年のこのタイミングで読んで、最も大きく心に残ったのは次の二つです。
まず、この本は2009年のISEFに出場したアメリカの若者たちを追っているドキュメントなのですが、実は2009年は唯一日本から代表を派遣しなかった年なのです。それは、アメリカを中心として新型インフルエンザがパンデミックになっていて、渡航を自粛したからです。(ちなみに2020年は5月にオンライン開催でしたから日本からも参加し、受賞したチームもあったそうです。)
2009年の新型インフルエンザは若者がかかりやすいと言われていて、日本で最初の感染者はカナダへ短期留学していた高校生たちでした。その学校の校長先生がテレビで泣きながら謝罪したのが当時有名で、そこに通っていた知り合いの子のお母さんが「うちの校長先生がかわいそうだ」と怒っていたのをよく覚えています。自粛警察的なムードがその頃もあったということですね。
夏前から捜真でもぽつぽつと感染者が出始めて、自然教室で数十人が感染したり若い先生が感染したりして一時は大騒ぎでしたが、日本では重症化する人が少なく、1年でほぼ沈静化しました。もちろん学校生活に今のような制限はありませんでした。
二つ目は、ISEF2009の出場者の一人がハンセン病だったということです。
BBというニックネームの16歳の女の子が診断を受けたときのお母さんの第一声、「まだハンセン病にかかる人がいるの?」が、まさに私の思いそのものでしでした。多磨全生園やハンセン病資料館に何度も行ったり話を聞いたりして、21世紀の今はよほど風土や衛生状態が悪い場合しか新たにかかる人がいないと思い込んでいたので衝撃的でした(実際、日本では新規感染者はほぼゼロ)。日本にも差別の歴史がありますが、アメリカでは聖書に親しんでいる分、根深い偏見があるそうです。らい菌という細菌は新型コロナや新型インフルエンザなどのウイルスとは異なり伝染力がきわめて弱いことや、ほぼ自然治癒すること、薬で伝染力は完全になくなることなどが、日本同様十分に知られてないのです。
毎週日曜日に礼拝出席するクリスチャンであるBBにとって、ハンセン病の知識は聖書のみ、それも悲惨なものばかりでした。恐れと悲しみのどん底に突き落とされた彼女は、気を取り直すとすぐに調べ始めました。結局、知識こそ力であり、事実を手に恐怖と戦うことを決意したのです。インターネットで調べ、本を読み、国立ハンセン病療養センターを訪れ、専門家に話を聞きました。ハンセン病について解明されていることはすべて、人間とアルマジロしかかからないことまで調べ尽くしました。そのうち、ドラマや映画など、いたるところで「『らい病患者』のように放り出す」のような悪い比喩としてハンセン病が取り上げられていることに気づいたのです。
そこからがBBのすごいところです。自分の次の課題は、ハンセン病に対する人々の誤解を解くことだと考えたのです。恐怖は感染症のように広がります。日本でも療養所に暮らしている元患者さんたちの多くは偽名ですし、アメリカでもハンセン病だということをほとんどの人が隠していて、知識のない医者がハンセン病患者を差別する例もあるそうです。そんな中、友人たちに「わたし、ハンセン病って言われちゃった。心配しないで。うつらないから。」と打ち明けたのです。
幸いあからさまな拒絶反応はありませんでしたが、無知ゆえに皆心配しました。彼女の病気の話はあっという間に広まり、脚の発疹をこっそり見られているのではないかと気になって黒タイツをはいた時期もありました。しかし、正しい知識が浸透するにつれ、「ハンセン病?クールだね!」みたいな感覚になっていったそうです。ハロウィーンの衣装をボロボロのローブを着て鈴を持った『らい病患者』(現在の新共同訳聖書では「重い皮膚病」となっている)にしたらどうかと提案してきたり、薬の副作用で尿がオレンジ色になると聞いて数人で個室についてきたり。そうこうするうちに発疹も消え、サイエンス·フェアに向けてハンセン病について一緒に研究しようと申し出る友人が現れました。この友人と二人で投薬によるらい菌の数の変化を調べる実験を重ね、州の大会へと勝ち進み、あらゆるメディアに取り上げられ、BBはついに国際学生科学フェア2009に乗り込むことになるのです。研究のくわしい内容は本を読んでくださいね。
12年前にもパンデミックがあったことを思い起こし、今でも病いそのものではなく無知と偏見にさらされて苦しむ人々がいることを改めて認識した私は、人間の弱さをつくづく思い知らされています。
私たちの体を作る細胞が日々新しくなるように、新たなウイルスが次々生まれています。環境破壊など大きく言えば人類が原因を作ったかもしれませんが、生きるために自粛要請に応じられない店の責任ではないし、ましてや留学を許可した校長先生のせいでもありません。
現在、医療従事者の方々が 感染力の強いウイルスと命懸けで闘い続けていらっしゃるのに、本人や家族が差別される事例が報道されています。一方、少なくとも日本では、ハンセン病に関わった医療従事者の中には一人もかかった人がいません。それほどまでに伝染力が弱いにもかかわらず、1996年にらい予防法が廃止されるまで危険手当が支給されていました。絶対安全なのにお金がもらえる、そのことを世間は知らない、知らせない方が得。それも廃止が遅れた理由の一つでした。とっくに治った方々が隔離され続け、世間は隔離が続いているから恐ろしい病気だと思い込まされていたのです。
他方で、本当に危険な福島の原発で命懸けの事故処理を続けていらっしゃる原発労働者の方々に、危険手当が支給されなくなっている現実もあります。最も危険な作業の多くは非正規雇用の方々が担っていて、1年間に浴びる放射線量の制限があるので雇用は不安定だし、政治の都合で待機させられても手当が出ない、経費削減で防護服や安全設備もどんどん劣悪になっていく。国の政策により稼働していた原発の後始末のため、制限があるとはいえ非常に高い線量を浴びているのに、病気になっても何の補償もないのです。危険手当もいらないくらいもう安全だ、オリンピックもできるくらいだ、とアピールする裏には、使い捨てにされている人々の存在があるのです。「ふくしま原発作業員日誌」もぜひ読んでください。図書館にあります。最初だけ英雄視され、次第に忘れられたり差別されたり···現在の医療従事者の方々に重なって、暗澹たる気持ちになります。
でも、若い皆さんがいる限り大丈夫です。
若者は経験や責任が少ない分、しがらみに縛られずに損得勘定を超えた発想や行動ができると思うからです。
BBはこう述べています。
「後悔ばかりして生きている人や、取り乱すばかりで問題解決に向けて一歩も踏み出さない人もいるでしょ。わたしは災難を引き寄せるタイプなんだけど、どんなときでも明るい面を見るようにしているのよ。」
ハンセン病にかかっても恥ずべきことではないと世界に訴えかえたBBは、「新しい挑戦を成し遂げるときに神を信じる心が勇気をくれた」とも語っています。同時に、窮地に追い込まれたときの救いは科学だったのです。
科学的な態度とは、「私は知らない」と謙虚に認識することだと思います。
知らないから調べ、知らないから学ぶ。
受け身でいるだけだと事実は隠されることもあるので、時には賢く疑う。
迷ったときはイエスさまを模範とする。
イエスさまは誰のことも、ハンセン病患者をも差別しませんでした。そのイエスさまが誰のことも見捨てないと約束してくださっています。キリストの復活が約束の証拠なのです。
だから、私たちは、キリストの約束を信じて喜んで今日の命を生き、分断ではなく平和を作り出していきましょう。
1月15日(金)中学部礼拝
チャペル ステンドグラス「神の心あらわれて」
皆様、明けましておめでとうございます。
さて、高等学部3年生の卒業記念品としてチャペルにステンドグラスの設置を計画していることは、すでに『学院報』などでお知らせいたしました。第71回卒業生(2018年度)から始まり、第72回生(2019年度)も加わってくださり、今後も長くかかる予定です。この両学年の卒業生の皆様にはすでにお話し申し上げました通り、学年ごとに1枚というのではなく、いずれ完成する11枚全体をその間の卒業生からご寄贈いただくという考え方で進めております。
テーマは校歌「神の心」です。2019年は山手34番で校歌が誕生して110年目、2020年は山手からこの中丸の丘に移転して110年目になるのを記念したいと考え、始まった計画です。全体のタイトルは「神の心あらわれて」とし、1枚ずつそれぞれに校歌の歌詞から題をつけることにいたしました。
その最初の2枚の設置が昨年末に行われました。後ろ扉から入って正面の十字架の作品を「神のやどりのしるしなるらん」、その隣を「富士の高嶺のかどべにま白く」といたしました。後者には富士山と110年前に山手から中丸に移植した藤棚が入っています。
実はいつかチャペルにステンドグラスをという話を私が最初に伺ったのは、数十年前、当時の理事長千葉勇先生と校長日野綾子先生からでした。それが今若い卒業生たちの卒業記念品として実現に着手できたのは嬉しい限りです。誠にありがとうございます。心から御礼を申し上げます。いずれコロナ禍が収束いたしましたら、皆様にぜひご覧いただきたいと存じます。
最後になりましたが、新しい年も皆様のご健康が守られ、神様の祝福が豊かに注がれますよう、お祈りいたします。
学院長 中島 昭子
オンライン クリスマス礼拝【動画】
皆様、クリスマスおめでとうございます。
新型コロナウイルスの影響で、例年とは違うクリスマスをお迎えのことと思います。捜真でも、高三だけがチャペルに入場し、合唱も行わないという初めてのスタイルでクリスマス礼拝を行いました。それでも、命と健康が守られ、生徒とともに礼拝をささげ、2学期を終えることができたことは大きな喜びであり感謝です。
今日も感染症の治療を受けていらっしゃる方、医療や介護に従事してくださっている皆様が、神様の御守りのうちに過ごされますようお祈りいたします。
中学部1年生作成のステンドグラスと中山校長のメッセージによるクリスマス礼拝の動画をお届けします。ぜひご覧ください。
中学部 1月9日(土)学校説明会 動画配信のご予約受けつけています
1月9日に予定されている中学部学校説明会は学校でのプログラムを中止し、すべてオンラインとさせていただきます。6年生を対象とした入試解説講座の様子を配信予定です。
KDM(Kids Dream More)子ども食堂にクリスマスプレゼント
有志団体のKDM(Kids Dream More)の活動で、子ども食堂の子どもたちにクリスマスプレゼントをお届けしました。
今年はコロナの影響で子ども食堂でのお手伝い活動ができないため、「自分たちにも何かできることはないか。」と考え、子ども食堂の子どもたちにクリスマスプレゼントを届けるという企画が始まりました。
募金活動、カード作りなど全校生徒が協力して、70個のクリスマスプレゼントと手作りカードを用意することができました。12月15日に大師新生教会の子ども食堂に集まる子どもたちにプレゼントが贈られました。
子ども食堂のスタッフから頂いたは心のこもったメッセージのカードをいただきました。
ENAGEED SUMMIT 社長賞受賞
この度、コロナ禍においても子どもたちの学びに向かう力を育むた
捜真女学校からは6組が出場し、1022組の応募の中から36組に絞られた第一次選考に、高一の3組が進みました。10組に絞られる第二次選考には1名が進み、12月19日に決勝が行われました。
当日のプレゼンテーションでは、「電車、バスの中で、学生でも、
この結果を受け、この生徒は京急電鉄にこの企画を提案しました。この座席の実現に向けて動き出しています。
小学校クリスマス礼拝
中1国語 「知識の樹木」調べ学習
2021年度中学部入試 面接の中止について
この度、本校では今節の新型コロナウイルスのさらなる感染拡大を受け、2021年度中学部入試の面接をすべて中止とすることを決定いたしました。筆記試験及び対話学力試験につきましては、募集要項の通り行う予定です。
受験をお考えの皆様には、入試直前の決定となりましたことをお詫び申し上げます。
○詳しくはこちらをご覧ください。2021年度中学部入試 面接の中止について
○募集要項·出願ページはこちらです。
礼拝メッセージ 12月18日
頭の中の小さな声
宗教主任 藤本 忍
【聖書】ルカによる福音書10章30節~37節
イエスはお答えになった。「ある人がエルサレムからエリコへ下って行く途中、追いはぎに襲われた。追いはぎはその人の服をはぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下って来たが、その人を見ると、道の向こう側を通って行った。同じように、レビ人もその場所にやって来たが、その人を見ると、道の向こう側を通って行った。ところが、旅をしていたあるサマリア人は、そばに来ると、その人を見て憐れに思い、近寄って傷に油とぶどう酒を注ぎ、包帯をして、自分のろばに乗せ、宿屋に連れて行って介抱した。そして、翌日になると、デナリオン銀貨二枚を取り出し、宿屋の主人に渡して言った。『この人を介抱してください。費用がもっとかかったら、帰りがけに払います。』さて、あなたはこの三人の中で、だれが追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。」律法の専門家は言った。「その人を助けた人です。」そこで、イエスは言われた。「行って、あなたも同じようにしなさい。」
********************************************
ある日、何となくYouTubeを開いていたら、「あなたにおススメ」という表示が目に入りました。「私の何を知っていて、そんなことを言うのだろう」と思いながらも、少し気になってポチっと「おススメ」を押してしまいました。すると、MIT(マサテューセッツ工科大学)の卒業式でした。大成功を収めた卒業生が母校に招かれて、祝辞を述べていました。英語の勉強にもなると思って少し聞いてみました。
「幸な人と言うのは成功を収めた人のことを言うのではなく、自分の挑戦を攻略している人のことを言うのだと思う。果敢に未知のものに挑んでいる人のことだ。それはまるでテニスボールを追いかける犬のようだ。リードを外された犬は、なりふり構わず無我夢中でテニスボールを追いかける。しかし、人間にとって厄介なのは自分のテニスボールが何なのか、わかりにくいということだ。」とりあえず聞こうと思っていた私でしたが、スピーチ中盤には彼の言葉に引き込まれていました。「何かに挑んだ時、準備万端だったということは一度もなかった。いつも何かが不足していた。しかし、それでも前に進まなければならなかったし、始めなければならなかった。」「人生でたった一回、正しければそれでいいのではないか。本当に正しかったその一回は、頭の中の小さな声に従ったときだった。消そうと思っても消えない小さな声、消えたと思っても再び浮かび上がってくる声、これが一番正しかった。そしてそれが僕のテニスボールだった。」
素晴らしいスピーチでした。ポチって押して本当に良かったと思いました。かき消しても打ち消しても何度でも浮かび上がっている声、自分にとってのテニスボール、皆さんにはありますか。先日の修養会でお話してくださった高一の講師の先生も、同じことを仰っていたのを思い出しました。「気になって気になって仕方のないこと、それがあなたのやるべきこと、使命なのかもしれない」と。
10月に入ったある日の日曜日、礼拝を終えた教会にインターホンが響きました。出て行くと小学校中学年位の女の子が二人いました。一人は自転車にまたがり、もう一人は素足で靴も履かずにいました。10月だと言うのに二人とも半袖半ズボンで、顔や腕が少し汚れていました。私が「こんにちは」と言うと、「ね~、ね~、子ども食堂はいつからやるの?」と聞かれました。「まだやらないの?コロナだから?」2月に中止にしたまま再開の目処が立っていなかったので、「再開する時は必ずこの掲示板でお知らせをするから、必ずここを見てくれる?」と言いました。「わかった。でも漢字は使わないでね。読めないから。」と女の子。「うん、わかった。漢字は使わないね。」と私。「ね、靴はないの?」ともう一人の女の子に聞くと「あるよ」と自転車の籠の中にある大人のサンダルを指差しました。「これは靴じゃないじゃない」と私が言うと「これが好きなの。これがいいの。」と返事が返って来ました。その子達とさよならした後、なぜか涙が溢れて来て止まりませんでした。泣き顔になる自分を必死に誤魔化しました。教会の主任牧師やメンバー達が「誰だったの?」と聞くので、「子ども食堂に来ていた子ども達です。」と伝えました。以来、私の頭の中の小さな声はこの「ね~、ね~、子ども食堂はいつからやるの」になっていきました。
それから2週間後の日曜日、教会でメッセージを聞いていたら、ある声が頭の中で響いてきました。それは「子ども食堂を再開しなさい。」という声でした。もしかしたら神様の声なのかもしれないと思いました。私は子ども食堂の責任者でもなければ、スタッフでもないのに。不思議でしたが、教会で子ども食堂に関わっている2人のご婦人に、そのまま話をしました。彼女達は直ぐにスタッフミーティングを開いて、12月15日には子ども食堂を再開することを決定してくれました。しかし、それから1ヶ月後の12月6日の日曜日、コロナ第三波を懸念して、再開は難しいと判断。中止が決まりました。束の間の糠喜びになってしまいました。いつになったら掲示板に再開の日を掲示できるのか。子ども食堂のスタッフ達は、一緒にご飯は食べられなくても、せめて食べる物は届けたいと、教会の前で月一回、缶詰やペットボトルの飲み物、個包装のお菓子などを無償で配ってくれています。そして、そのような中、捜真のKDM(Kids Dream More)の生徒達が献金を募って、クリスマスプレゼントを届けてくれるという知らせが聞こえてきました。大きな喜びです。こういう時だからこそ、人の優しさが心に沁みます。
今日お読みした聖書箇所にはサマリア人を突き動かす動機として「憐れに思う」という言葉が使われています。原語では「五臓六腑が引きちぎられるほど痛い」という意味です。相手の痛みが瞬時に伝わってきて、思わず動いてしまう、そういう衝動的な行動の根拠を表す動詞です。私の頭の中の声、そして私のテニスボールは、私の五臓六腑を締めつけたあの女の子の一言です。「ね~、ね~、子ども食堂はいつやるの?」神様からのクリスマスプレゼントとだと思い、私はこの言葉を犬のように追い駈けていきます。
お祈りします。
神様、本当に助けが必要な人達の所に、あなたの救いが届きますように。
その為に私達を用いて下さいますように。
(12月9日(水)全校放送礼拝)
緊急企画!! ~在校生保護者によるオンライン個別相談【中学部入試】~
学校生活や入試についての気になることを、在校生保護者に聞いてみませんか?
20分間、在校生の保護者を独り占めで、直接お話しいただけます。
ぜひ、捜真の新たな一面を知ってください。
今週土曜日、12月19日(土)
① 10:00~10:20
② 10:30~10:50
③ 11:00~11:20 の全3枠
限定9組の企画です!
予約は toiawase@nkmr8.sakura.ne.jp へ
タイトル 保護者オンライン個別
本文 ① お嬢様のお名前
② 学年
③ 保護者氏名
④ 時間枠の希望を第1~第3まで
⑤ 電話番号
*toiawase@nkmr8.sakura.ne.jp からのメールを受信できるように設定をお願いいたします。
予約が確定した方には、メールでご連絡致します。
なお、当日はZoomを使用いたします。
図書委員 ユニセフ協会 #あつまれ神奈川2020ハンドインハンドに参加
礼拝メッセージ 12月15日
目に見えない大切なもの
中1生徒 A·S
【聖書】ルカによる福音書6章28節~31節
悪口を言う者に祝福を祈り、あなたがたを侮辱する者のために祈りなさい。あなたの頬を打つ者には、もう一方の頬をも向けなさい。上着を奪い取る者には、下着をも拒んではならない。求める者には、だれにでも与えなさい。あなたの持ちものを奪う者から取り返そうとしてはならない。人にしてもらいたいと思うことを、人にもしなさい。
********************************************
私はクリスマスが大好きです。「私」というより家族みんなが大好きです。すでに私は10月中旬あたりからクリスマス気分でした。ハロウィンよりクリスマス、なんならお正月よりクリスマス。どの行事と比べても、だんとつでクリスマスが好きな気がします。というわけで先日、ツリーを買い替えて、私の家には華やかなクリスマスツリーが設置されています。でも、なぜそんなにクリスマスが好きなの?ともし聞かれても、すぐに答えられる自信はありません。どこに惹かれてそんなにクリスマスが好きなのか、自分でもさっぱり分からないけれど、なんでか小さいころからずっと好きでした。
さて、クリスマスといわれて皆さんが最初に思い浮かべるものは何でしょう。私だったらサンタクロースとかプレゼントとか、そんな言葉が真っ先に浮かんできます。そのサンタクロースのことで、私は思うことがあります。
よく「サンタクロース信じている?」と聞かれることがあります。私が好きな本の一つに、『サンタクロースっているんでしょうか?』というものがあります。その本は、アメリカのニューヨーク·サン新聞という新聞社が、ある8歳の少女の質問に答えたという社説です。今から100年ほど前の実話ですが、今でも世界中の人に愛読されています。新聞社に質問を出したバージニア·オハンロンさんは友だちに「サンタクロースなんていないんだ」と言われ、新聞社に聞いてみることにしたと言っています。そして新聞社は「その友だちはまちがっています。」と答えています。
この本の中に、「この世界でいちばんたしかなこと、それは子どもの目にもおとなの目にもみえないものなのですから。」という部分があります。私はそこを読んだ時に、すごく心にのこりました。この世界は目に見えるもの、手でさわれるものであふれています。でも、その逆に誰も見たことがなく、さわったことのないサンタクロースは、一見、「人が頭の中で作り出し、想像したもの」に見えます。しかし、本当はそうではなく、目に見えない世界を覆いかくしている幕を開けようとしていないだけなのです。そしてその幕をひきのけられるのは、信頼と想像力と詩と愛とロマンスだけなのだとサン新聞社の記者は言っています。多くの人は「目に見えない大切なもの」を見ようともせず退けています。でも、たとえ生活の中で苦しいこと、辛いことなどがあっても、少しの間、そのことを忘れ、目に見えないものを想像し、信じることで悲しい気持ちがうそだったかのように晴れ渡ります。それがほんの一瞬で、すぐにつらい現実を思い出してしまったとしても、ただの一秒であっても幕の向こうを垣間見ることができたなら、それは本当に素敵なことだな、と感じます。私は目に見えないものの大切さに気付ける人でありたいです。
(今日ご紹介したのは、11月の中1クラス礼拝でのお話です。)
PTA・同窓会クリスマス礼拝は中止とさせていただきます
保護者の皆様·卒業生の皆様
お変わりなくお過ごしのことと存じます。いつもお祈りとお支えを感謝申し上げます。
さて12月22日(火)に予定しておりました「PTA·同窓会クリスマス礼拝」は、新型コロナウイルス感染防止のため中止とさせていただきます。どうぞご了承くださいませ。